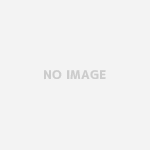競走馬のなかには早熟馬や晩成馬と呼ばれる馬がいます。
昔からある言葉ですし、競馬ゲームなどにも頻繁に出てくるので聞いたことはあるかと思います。
ただ、競馬初心者からすると、どういう意味かは分からないでしょう。
ここでは、競馬の早熟と晩成について紹介します。
早熟とは

早熟とは、一般的にピークが2~4歳の競走馬のことを指します。
競走馬にはそれぞれピークの時期がありますが、多くの競走馬のピークは4~6歳と言われています。
一方、早熟馬は4~6歳の時期にはピークが過ぎ去っており、パフォーマンスが著しく下がってしまいます。
早熟馬の流れ
競走馬は2歳の6月からデビューすることができます。
早熟馬は早い時期に体が出来上がるので、デビューの時期も早いです。
そして、早い時期にデビューし、勝ち星を重ね、2歳重賞などに出走したのちに、2歳チャンピオンを決めるG1阪神ジュベナイルフィリーズや朝日杯などに出走します。
3歳時は日本ダービーなどをクラシックを目指す馬が多いですが、2歳がピークの超早熟馬はクラシックで散々な結果となってしまいます。
一方、3歳がピークの早熟馬はクラシックで活躍できますが、4歳になって上の世代の馬とバチバチにやり合う時期にはピークが過ぎ去り、活躍できません。
もちろん、早熟馬と言っても、能力の上限が低い馬は2歳、3歳でも活躍できないまま、引退していきます。
または、好走するものの、勝ち切れずに上のクラスに行けないままピークが過ぎ、引退するパターンもあります。
最近の早熟馬
近年の早熟馬と言えば、マカヒキやナムラリコリス、ロンドンプランが挙げられます。
マカヒキの成績
| 年齢 | 成績 |
| 2歳 | 新馬戦(1着) |
| 3歳 | 若駒S(1着)、弥生賞(1着)、皐月賞(2着)、日本ダービー(1着)、ニエル賞(1着)、凱旋門賞(14着) |
| 4歳 |
京都記念(3着)、大阪杯(4着)、毎日王冠(6着)、天皇賞秋(5着)、ジャパンカップ(4着) |
| 5歳 |
札幌記念(2着)、天皇賞秋(7着)、有馬記念(10着) |
| 6歳 |
京都記念(3着)、大阪杯(4着)、宝塚記念(11着)、天皇賞秋(10着)、ジャパンカップ(4着) |
| 7歳 |
大阪杯(11着)、ジャパンカップ(9着) |
| 8歳 |
天皇賞春(8着)、京都大賞典(1着)、ジャパンカップ(14着) |
| 9歳 |
京都記念(11着)、大阪杯(14着)、札幌記念(16着) |
マカヒキはデビューから3連勝するなど活躍し、2016年には日本ダービーを勝ち、3歳馬の頂点に立ちました。
その後、フランスで行われた凱旋門賞に挑戦するもの敗れ、4歳以降はそれなりに走るものの、凡走ばかりでした。
8歳時に京都大賞典を勝ちますが、メンバーレベルや3歳時のマカヒキの活躍を考えると、手放しで喜べる結果ではありません。
また、海外遠征のせいでおかしくなったという意見もありますが、ただ単に早熟馬だったのだろうという意見の方が多いです。
ナムラリコリスの成績
| 年齢 | 成績 |
| 2歳 | 新馬(2着)、2歳未勝利(1着)、函館2歳S(1着)、阪神JF(17着) |
| 3歳 | 紅梅S(6着)、ファルコンS(18着) |
ナムラリコリスこそ典型的な超早熟馬です。
2歳の夏がピークで、そこからは一気に成績が悪くなっていきました。
牝馬だったため、早めに見切りがつけられて繫殖に行きましたが、あのまま現役を続けても大きな結果を残すのは難しかったと思います。
ロンドンプランの成績
| 年齢 | 成績 |
| 2歳 | 新馬(1着)、小倉2歳S(1着)、京王杯2歳S(14着) |
| 3歳 | 北九州記念(8着)、セントウルS(5着)、信越S(8着) |
| 4歳 | カーバンクルS(15着)、北九州短距離S(15着)、松風月S(13着)、みちのくS(12着) |
| 5歳 | 北九州短距離S(8着)、鞍馬S(8着) |
ロンドンプランもピークが2歳の秋でした。
4歳時にはダートも試したりしていましたが、結果は出ていないため、適性云々というよりは純粋に早熟馬だったと言えます。
早熟馬の復活
早熟馬でも年を取ってから急に復活する馬がいます。
たとえば、タイムフライヤーという馬は2歳時に活躍し、2歳G1も勝ちましたが、3歳時は皐月賞10着、日本ダービー11着とさっぱり活躍できませんでした。
4歳時も結果が出ませんでしたが、ダートに転向すると5歳時にはOPとG3を連勝するなど復活しました。
競馬のダートとは?ダートについてまとめてみた【ダートG1一覧】
このように、芝馬からダート馬に変えたり、中央競馬から地方競馬に移籍するなど環境を変えると復活する早熟馬もいます。
ただ、こういう馬は早熟馬ではなく、ただ単に適性が合っていなかっただけの場合もあります。
晩成とは

晩成馬とは、高齢になってから活躍する競走馬のことを指します。
早熟は2~4歳がピークですが、晩成は5~7歳がピークと言われています。
競馬は勝つたびに上のクラスに進むことができますが、ずっと未勝利だと出られるレースが少なくなり、地方への移籍や引退を余儀なくされます。
なので、晩成馬はピークが来る前に競走馬として終わる可能もあります。
また、晩成馬か否かはたびたび論争になります。
たとえば、2020年に引退したリスグラシューという馬は5歳でG1を3連勝しましたが、2歳時にも重賞を勝ったりG1で2着に来ています。
なので、能力のある馬に関しては晩成なのかどうかは判断しづらいです。
晩成馬の流れ
晩成馬は基本的にデビューが遅く、3歳春にデビューする馬も多いです。
晩成馬の場合は条件クラス(1勝クラスや2勝クラス)で地道に走っていく馬が多いです。
そして、経験と年齢を重ねるにつれ力をつけていき、重賞を勝つようになっていきます。
晩成と言っても6歳でピークを迎え7歳で衰えていく馬もいます。
最近の晩成馬
最近は早熟な傾向が多いので、目立った晩成馬はあまりいません。
マニアックなところだと、サイモンラムセスが挙げられます。
サイモンラムセスは8歳の2月まで55戦して3勝しかできませんでしたが、8歳の5月に突如覚醒し、2連勝しました。
そして、9歳のころにはG3小倉大賞典で3着、引退レースとなったG3鳴尾記念でも10歳ながら4着に入りました。
早熟か晩成かの見分け方
早熟馬か晩成馬になるかは血統にされやすいです。
ハーツクライ産駒は晩成型が多いと言われていますし、Frankel産駒は早熟型が多いと言われています。
たとえば、Frankel産駒だと2歳・3歳で活躍して4歳以降は全く活躍できなかったソウルスターリングやミスエルテが挙げられます。
ただ、産駒によってある程度傾向が決まってきますが、母方との配合によって、変わってくる場合もあります。
他にも、調教師や騎手のコメントから早熟か晩成かを判断することもできます。
2歳・3歳の時に「すでに完成されている」と言ったコメントがある場合は早熟ですし、「本格化は当分先」や「まだまだこれからの馬」の場合は晩成と判断できます。
また、ウイニングポストなどの競馬ゲームでは早熟や晩成が重要な要素の一つとなっています。
どうやって早熟の馬を誕生させるかなどを考えてプレイするので、どの配合で早熟や晩成になるかを勉強することができます。
まとめ
早熟は2歳~4歳がピークの馬で、晩成は5歳~7歳がピークの馬です。
早熟の場合は2歳重賞やクラシックで活躍できますが、現役の期間は短いです。
晩成の場合は現役期間は長いですが、ケガなどによってピークを迎えることができない可能性もあります。
早熟や晩成かは血統などから判断することが可能です。